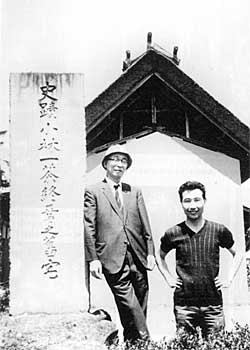
昭和38年 師・宇田零雨(左)と
小林一茶終演の旧宅で

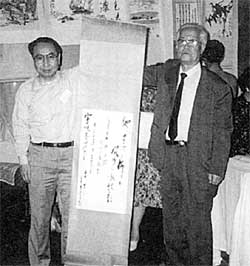
平成2年 中国和歌・俳句研究家の李芒氏が
冬男の中国吟を軸にして贈呈(北京)

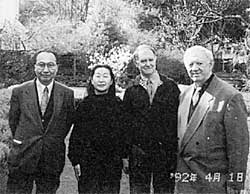
平成4年 日英俳句交流で当時の英国俳句協会会長らとロンドン郊外の詩人・キーツの家で。左から冬男、加藤耕子

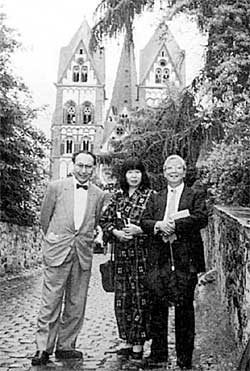
平成4年 日独俳句・連句シンポジウムの講師として渡独。左から冬男、黒田杏子、荒木忠男


平成4年 印度仏跡巡礼の旅。兄・小久保康田大僧正夫妻(左)とベナレスにて。兄は常光院に句碑を建立。

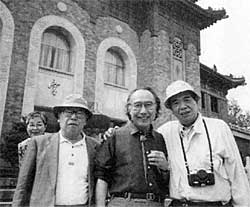
平成8年 日中俳句・漢俳交流会(北京)。左から金子兜太夫妻、冬男、相原左義長


平成9年 在日米公邸で前アメリカ俳句協会会長デミング夫人の送別会。
左から竹下流彩、石原八束、冬男、白石かずこ、有馬朗人、大矢章朔、近藤蕉肝
|
●師・宇田零雨との出会い

昭和二十四年、常光院を会場に若菜会という文化サークルがあった。読書会、音楽鑑賞会、ダンススクールなどを催すと同時に、句会も行事の一つ。
この句会に誰かゲストを呼びたい、ということになり、零雨が指名されたのである。
零雨は文芸投稿誌「文章倶楽部」の俳句欄を担当していた。宇咲さんは小説投稿のかたわら、俳句にも挑戦していたので、零雨の名前はよく知っていた。後日、

室の花愛し飛雲にふれあえず

で、零雨の一席に入選している。
幸いなことに零雨は、月に何回か埼玉大学へ俳句の指導に来ていた。お願いすると、気安く常光院を訪ね、
「俳句は芭蕉を読めば独学でも勉強が出来るが、連句は独りでは出来ない」
と言って、泊まりがけで連句の手解きをしてくれた。
文学好きの宇咲さんには、物語性のある連句が面白く、たちまち虜となって、零雨主宰の「草茎」に入会し、
東京・世田谷の零雨の自宅の句会にも出席するようになった。

椿落ち詩のよみがえる歩を得たり
金魚居て孤独の脆坐のさだまらず
行けどゆけど大虹のしたぬけきれず

その頃の作である。

●最愛の妻を得る

吹雪く夜を愛してならぬひと愛す

昭和三十一年の作。相手は老母と二人暮らしの西川流師範の西野咲子。一人娘ということで、双方の母親は反対。しかし、翌年は、

春の雲湧きてはあふる華燭の日

となった。そして、翌年には、

梅雨に籠り父となることふと怖ぢぬ

『自註・宇咲冬男集』には、「妻から受胎を告げられた。不規則な生活から十二指腸潰瘍になっていたときでもあり、
うれしさと生活の不安とで複雑な気持だった」とある。
やがて努力が認められて、東京本社の社会部勤務となり、そして署名入りの記事も書くようになる。
しかし、ますます忙しくなる一方で本命の小説は書けなかった。

吐く息の白し今日より事件記者
昼火事や衆愚の中に記者もゐし
冬銀河寝顔のほかは子と逢へず

●新聞社を辞職

昭和三十八年、宇咲さんは過労と十二指腸潰瘍の再発で倒れた。医師から入院を勧められたが、それを押して仕事に励む程の猛烈社員だった。
しかし、仕事に没頭すればする程、虚しさも大きくなる。こんなことをしていると、いつまでも小説が書けない。なんのために兄と喧嘩してまで寺を出たのか。
入社して十年目、宇咲さんは清水の舞台から飛び降りる覚悟で、新聞社を辞める決心をした。
さぞ、反対すると思った妻は、「そんな気がしたわ」とあっさり言ったのみ。
宇咲さんは早速、企画会社「明広」を設立する。といっても、社員四、五人程度の零細企業であった。
記者時代のコネを使ってデパートのPR誌や大手企業のパンフレットなどの製作を引き受け、できるだけ余暇を作って創作に熱中した。
しかし、何事も甘くはない。仕事が忙しくなると、小説どころではなかった。
そんな折、友人から「俳句がたまっているんだろう。俺のところから出さないか」と勧められたのが第二句集『梨の芯』である。
版元が現幻社という詩集専門の出版社だったので、詩集と間違って買った読者から「俳句を学びたいが、どうしたらいいのか」という問い合せが続出した。
思いがけない展開に、宇咲さんはとりあえず自分の事務所に俳句講座を開設した。これが昭和五十年の月刊誌「あした」に発展するのだ。

●三度目の正直

昭和五十五年、俳句と連句の世界のみに生きる決心で、十七年続けた「明広」を閉鎖。勿論、小説を断念した訳ではない。
しかし、小説を職業とする志向は薄れて、詩歌の世界が自分の生きる最善の道だと思うようになった。
しかし、師・零雨から「俳句を貫くつもりなら、俳壇つきあいはするな」と止められていた宇咲さんの評価は、俳壇ではあまり高くなかった。
ともすれば連句人のように思われていたのを、印度、韓国などの旅吟を中心とした七○九句を収録した第四句集『乾坤』で跳ね返した。
その嚆矢が、総合誌「俳句」(角川書店)に載った瀬戸内寂聴の『乾坤』評であった。寂聴は「私は宇咲氏のかくれファン」だと称し、
「私は度重ねている自分の印度巡礼の日々を思い出し、こうも的確に短詩に感動を極めつくす氏の才能に嫉妬を覚えた」とエールを送り、

裸木ゆゑ風にも日にも光るなり
巡礼へこころもろとも跣足なり
乾坤の一滴となり裸なり
銀河恋ふ星のひとつに棲みながら
縫ひ針の光る細さの今朝の冬

など、宇咲さんのあらゆる面を引き出して懇切に批評した。宇咲さんはこれで俳壇に認められるようになったという。
宇咲さんは旅吟を得意とし、機会あるごとに旅を繰り返した。それは海外十五ヶ国までに及び、平成十年にはドイツのフランクフルト郊外に、

薔薇は実に人活き活きと薔薇の町

の句碑を、バート・ナウハイム市が建ててくれた。同市は世界でも有数の薔薇の産地だから、絶好の記念になった。
芭蕉の『野ざらし紀行』に憬れている宇咲さんは、まだ初心を諦めていない。大作は墓の下で熟考するとしても、
輝く一篇は期待出来る。常に「あした」に賭ける宇咲さんの今後を楽しみにしたい。


|
昭和59年 中国古都巡礼と吟行の旅で。
暉崚康隆氏(左)と(西安)
|